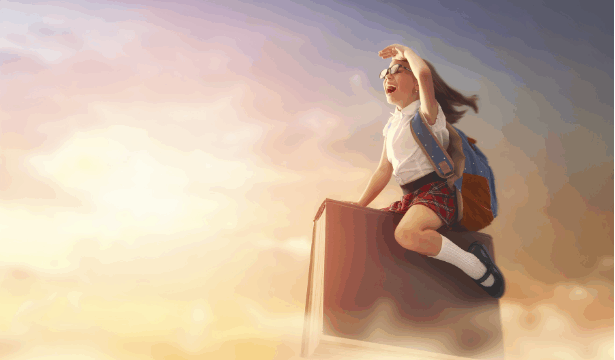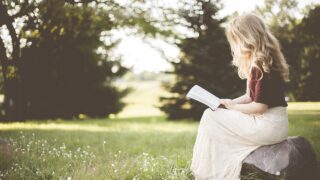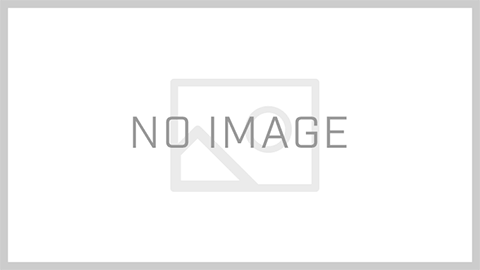こんにちは、きあらです。
離婚をきっかけに、娘と人生を立て直すべく「在宅ワーク」を選び、
現在はフリーランスとして、海外で暮らしています。
シングルマザーとして、海外移住をする!と決断したとき、
「子どもの英語が大丈夫なのか?」
「学校で困ったりしないかな?」
という不安が大きかったです。
きっと、同じように考えているシングルマザーの方も多いのではないでしょうか。
実際、私は、
移住を考える中で「子どもにはどれくらいの英語力が必要か?」という疑問にぶつかり、
お金も時間もかけられない中で、どんな準備をすれば安心できるのかを調べました。
そして、シンプルに「移住前にできる限りの準備をしておこう」と決めました。
私は、いわゆる「教育ガチ勢」ではありません。
教育移住といのでもありません。
でも、移住するのであれば、移住後に子供にしんどい思いはしてほしくない。
この記事では、シングルマザーの私が実際に、子供のために行った
時間もお金もかけず行った英語勉強法をお伝えします。
結果、移住後、娘はオールイングリッシュの洗礼は受けましたが、
比較的早いタイミングで英語がベッラベラになりましたので、
英語に不安を感じている方に、少しでも、参考になれば嬉しいです。
ほぼ英語が話せないレベル|小学生3年生で移住した私たちの英語教育

移住を決めたとき、娘は小学校2年生。
その年齢で海外移住をすることに対して、
英語力への不安はもちろん大きかったので、
そして、約1年間の準備期間をあて、できるだけ英語に触れさせようと考えていました。
でも、振り返ってみると、英語の上達のための秘訣は、
未就学児の頃からの習慣が大きいと感じています。
まずは、英語学習の地盤づくりから。
そこからお話しします。
いきなり英語を覚えさせるのは無理——まずは、読書習慣と集中力

小さい子どもに英語をいきなり覚えさせるのは無理です。
それでも、移住したら、英語は絶対に勉強することになります。
そのために、
まずは、移住前にやっておくべきだったのは、
英語力を育てるための地盤づくりで、
それは、母国語でスタート。
日本語でできることから始める
シングルマザーとして、パートの掛け持ちで毎日疲弊していた私には、
図書館に行って本を読んであげる体力はありませんでした。
でも、唯一、娘のために時間をとっていたのが、寝かしつけの時の絵本読み。
この時間が、後々、娘の読書習慣に繋がっていきました。
寝かしつけの絵本読みがどのように、その後の英語学習につながっていったのかは、
この通り↓
| 年齢/時期 | 読書内容 |
|---|---|
| 未就学〜小2 | 寝かしつけ絵本読み |
| 小3前半 | 「なぜなに?」シリーズを一緒に読む(字が小さくなってくる、そろそろ私が限界に・・) |
| 小3後半〜 | 「なぜなに?」シリーズを自分で読むようになる、英語の簡単な漫画やシリーズを読み始める |
| 小4〜 | 徐々に日本語から英語の本にシフトしていき、色々なシリーズに挑戦するようになる |
| 小5 | 自分のお気に入りのシリーズの本を自分で見つけてきて読むようになる |
読書を習慣することが何故大切か、というと、
読書習慣は、じっと何十分も同じ姿勢で同じ行為をし続けることを可能にするからです。
授業、テスト、全て長時間集中して座ってられるか、の問題から始まります。
なので、
YouTubeなどのテンポの早い動画は見せず、
じっくりと読書に集中できるように心がけました。
紙芝居や劇の効果——集中力を育てるのに効果抜群
さらに、集中力を高めるために有効だったのが「紙芝居」や「劇」です。
私は紙芝居を読んであげる余裕がなかったのですが、
ありがたいことに、娘は園でたくさん紙芝居を読んでもらっていたようです。
これらは、集中してひとつの物語に向き合わせる良い練習になり、
子どもが物語をじっと見て聞くことで、注意力や集中力が自然に育まれました。
紙芝居や劇の良い点
-
集中力の向上:ひとつの物語をじっと見て聞くことで、注意力や集中力が鍛えられます。
-
言語力の発達:きれいな日本語や語彙、表現に触れる機会となり、語彙力や文の構造を自然に学べます。
-
協調性・マナーが育つ:静かに見る、順番を守るなどの集団行動の基本を学ぶことができます。
紙芝居を見た後には、必ず「どう思った?」「あの子はどんな気持ちだった?」といった対話をするのも大切と言われています。
そうすることで、お話を聞く、見る、ということが受け身では終わらないで、
きちんとアウトプットの習慣につながっていき、語彙力を増やすことに繋がっていきます。
まずは、読書習慣と集中力をつけて、地盤づくり
ラジオ、基礎英語の教材で勉強

移住前に、英語力を伸ばすために私たちが取り入れたのが、
NHKラジオの基礎英語でした。
優しい内容で、聞いているだけでも英語の感覚が身につきました。
私は最新号を買う余裕がなかったので、
メルカリで、過去の1年分の教材を購入しました。
具体的にやったことを書いておきます。
ラジオ講座で習慣化の基礎づくり
朝起きたらや、下校したらと、決まった時間に聴く習慣を作りました。
聞いているだけで、リスニング力はもちろん、
英語の感覚を自然に身につけることができました。
先生も明るく、テーマもおもしろく、急に難しくなることもなく、
「全部わからなくていい、まずは習慣化すること」が大事だと感じました。
この習慣ができていなかったら、
インターナショナルスクールでオール英語の生活についていくのは難しかったと思います。
文字をなぞる
ラジオ教材の中には、文字をなぞる箇所がありました。
最初は「なぞるだけ?」と思っていましたが、これが意外にも役立ちました。
なぞることで速く書けるようになります。
移住後、英語の授業で先生が板書する内容を素早く写す力がつきます。
実際に、授業で板書した内容をとにかく写して帰ってきたことが、
英語力を高める一助になったと感じています。
NHKラジオの基礎英語で、学習の習慣化と早く書く練習
フォニックスで音と文字をしっかり学ぶ
 小3のタイミングで海外にきて、「push」という単語が読めない子がいました。
小3のタイミングで海外にきて、「push」という単語が読めない子がいました。
その時、先生方が呆れた表情をされているのを見て、怖くなりました。
うちの子はちゃんと読めているだろうか。と。
そう、インターに入ったらなんとかなる、は甘い!
実際、呆れた顔をされたりして、傷つくのは子どもたちなのです。
幸い、娘とは、フォニックスの本を一緒にみたり、
Eテレの英語番組をみたり、
ラジオでわからないなりにも、何度も耳に入ってきていたので、
「push」が「プッシュ」となる、
「cat」 が「キャット」になる、ということを理解していました。
「sh」が「シュ」になることを知らずに英語を学ぶと、非常に苦労します。
フォニックスでは、音と文字の対応をしっかり学べるので、
子どもが英語の発音やつづりを自然に覚えていきます。
特に「sh」のような音を理解するためには、フォニックスが非常に有効です。
フォニックスの教材は、これまた、ラクマやメルカリで安く手に入れることができます。
コストを抑えながら効果的に学習を進められます。
フォニックスで、最低限の発音と読み方の基礎を知っておく
日本人の先生で、安心して英会話の基礎を学ぶ

英会話は、移住前の最後の3ヶ月でスピーキングの練習を行いました。
知り合いの、英語の先生になりたい方を紹介していただき、
格安でお願いしました。
英語初心者の娘ににとって、いきなり外国人の先生とレッスンを始めるのは、
どうしても不安や抵抗感が大きいものです。
移住前に英語が嫌いになったら大変です。
日本人の先生だと、英語に対する不安が少し軽減され、
スムーズに学びを進めることができます。
日本語で丁寧に教えてもらいながら進めることで、
拒否反応を起こさず、リラックスして学ぶことができました。
先生をつけるなから、外国人より日本人の先生から。
わからなければ聞ける体制で!
まとめと反省点

このように、移住を視野に入れて、英語の勉強を始めました。
仕事をしながら、移住準備をしながらとなると、
つきっきりで見てあげることができません。
そんな中での最低限やれたことをまとめます:
・リーディング
日本語の本でまずは読書習慣をつけておくことが大切です。
読書は、集中力や語彙力を養う基盤となり、英語学習にも大いに役立ちます。
・ライティングとヒアリング
まずはフォニックスで音と文字の対応をしっかり学び、
なぞることから始めて、早く書けるようにしておくことが重要です。
なぞる練習が板書を素早く写せる力を養い、ヒアリング力も向上します。
・スピーキングとヒアリング
日本人の先生と英会話を話すことで、安心してスピーキングを練習できました。
英語初心者にとって、日本語でのサポートが大きな助けになります。
反省点
圧倒的にヒアリングの量が少なかったのが反省点です。
移住後に、浴びるようにヒアリングの量を増やしましたが、
日本にいる間からもっと英語で何かを観たり、
聞いたりしておけばよかったと後悔しました。
皆さんはぜひ、移住前から英語に触れる時間を増やしてくださいね。
これが、後々大きな差になります!
おわりに

よっぽどネイティブでない限り、
インターナショナルスクールに入れば、どちらにしても苦労はあります。
でも、集中力や学習の習慣化、フォニックスがあるのとないのでは、
その後の伸び率が圧倒的に変わってきます。
どれも、教育ガチ勢のように、つきっきりでやる必要はありません。
私は、娘といい時間を過ごす延長線上にすべてありました。
とにかく、英語を嫌いにならないように!
それだけ心がけていました。
一緒にがんばりましょう!
次回は、移住後の英語学習方法についてお話ししますね。